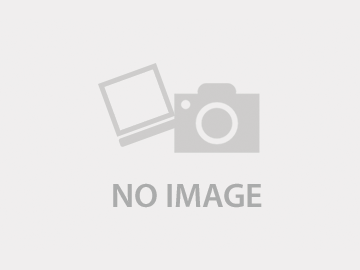新暦4月8日 (旧暦2月20日 寅)
皆様 日々の祈り合わせにご賛同いただきありがとうございます。
今回より、自然災害グループからの記事を「自然からの学び」として発信させていただきます。
以降、よろしくお願いします
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … * …* … * … *
現代は地震活動が活発な時期に入ったと言われている。そして「東京直下地震」「南海・東南海・東海地震」も近いと叫ばれている。日本列島は地震国だが、この地震活動は活発な時期と静穏な時期がある。
では、活発な時期はどのような時代だったのだろうか?近い過去では幕末の頃があげられる。この安政年間は日本で多くの地震が発生した時代である。安政江戸地震(1855年) (M7)の前年である安政元年(1854年12月23日)には安政東海地震(M8.4)、その32時間後に安政南海地震(M8.4)が発生しており、安政江戸地震と合わせて「安政三大地震」と呼ばれる。また安政南海地震の2日後には、現在の大分県と愛媛県の間にある豊予海峡のやや大分寄りで豊予海峡地震(M7.4)も起きている。この他にも安政年間には安政元年(1854)に伊賀上野地震(M7.4)、安政2年に飛騨地震(M6.8)等も起きている。
この時代はどのような世の中だったのだろうか?1853年(嘉永6年)にペリー率いる黒船が現れ徳川幕府は騒然として、水戸過激浪士を中心に「攘夷」が叫ばれ始める。そして1860年には井伊直弼の「安政の大獄」が起きる。これをきっかけに「倒幕」へと時代は流れていく。一般庶民は「ええじゃないか」の集団で街々を巡って熱狂的に踊る現象が起きた。
また第二次世界大戦中には1944年に昭和東南海地震、そして1945年前後にかけて4年連続で1000名を超える死者を出した4大地震(鳥取地震、三河地震、南海地震)が発生している。
このように世の中や人心が乱れている時には、大きな自然災害が多発している。果たして今の時代はどうだろうか?
自然災害担当グループより
皆様 日々の祈り合わせにご賛同いただきありがとうございます。
今回より、自然災害グループからの記事を「自然からの学び」として発信させていただきます。
以降、よろしくお願いします
* … * … * … * …* … * … * … * …* … * … * … * … * …* … * … *
現代は地震活動が活発な時期に入ったと言われている。そして「東京直下地震」「南海・東南海・東海地震」も近いと叫ばれている。日本列島は地震国だが、この地震活動は活発な時期と静穏な時期がある。
では、活発な時期はどのような時代だったのだろうか?近い過去では幕末の頃があげられる。この安政年間は日本で多くの地震が発生した時代である。安政江戸地震(1855年) (M7)の前年である安政元年(1854年12月23日)には安政東海地震(M8.4)、その32時間後に安政南海地震(M8.4)が発生しており、安政江戸地震と合わせて「安政三大地震」と呼ばれる。また安政南海地震の2日後には、現在の大分県と愛媛県の間にある豊予海峡のやや大分寄りで豊予海峡地震(M7.4)も起きている。この他にも安政年間には安政元年(1854)に伊賀上野地震(M7.4)、安政2年に飛騨地震(M6.8)等も起きている。
この時代はどのような世の中だったのだろうか?1853年(嘉永6年)にペリー率いる黒船が現れ徳川幕府は騒然として、水戸過激浪士を中心に「攘夷」が叫ばれ始める。そして1860年には井伊直弼の「安政の大獄」が起きる。これをきっかけに「倒幕」へと時代は流れていく。一般庶民は「ええじゃないか」の集団で街々を巡って熱狂的に踊る現象が起きた。
また第二次世界大戦中には1944年に昭和東南海地震、そして1945年前後にかけて4年連続で1000名を超える死者を出した4大地震(鳥取地震、三河地震、南海地震)が発生している。
このように世の中や人心が乱れている時には、大きな自然災害が多発している。果たして今の時代はどうだろうか?
自然災害担当グループより