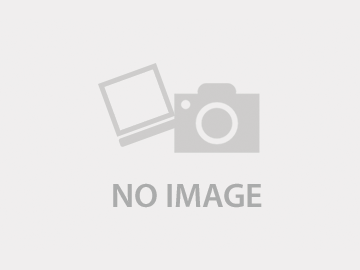いつもブログ・メルマガをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、8月22日現在、噴火警戒レベル4(避難準備)が出されている桜島について取り上げてみたいと思います。
1.桜島の成り立ち
桜島は、鹿児島湾北奥部の姶良カルデラ南縁部に生じた東西約10km、南北約8kmの長円形の島で、その頂部は最高峰の北岳と中岳、南岳の3峰と権現山、鍋山、引ノ平などの側火山からなっています。
桜島が活動を開始したのは、姶良カルデラが大噴火した後の約26,000年前からで、初めは海底火山だったものが大規模な噴火を繰り返して、隆起して島になりました。現在までに大規模な噴火を17回繰り返しており、その中での最大の噴火は、今から約13,000年前の大噴火で、この時には現在の鹿児島市内で1m以上、鹿児島県内の殆どの箇所で10cm以上の火山灰が積もりました。
桜島の活動は大きく二つの時期に分かれており、誕生から5000年前までが北岳の活動、約4500年前からは南岳を中心とした活動期に入り、断続的な噴火と静穏な状態を繰り返しています。有史以後の山頂噴火は南岳で起こっており、その都度、溶岩流や火砕流による大災害となっています。
記録に残る主な活動としては、最古の噴火は和銅元年(708)、15世紀後半の文明大噴火、安永8年(1779)の安永大噴火があり、噴石や降灰により多数の死者を出しています。この安永大噴火は18世紀の日本最大の噴火で、海底噴火による津波が発生し、鹿児島県沿岸部でも多くの被害が生じました。更に大正3年(1914)の大正大噴火、また昭和に入ってからも噴火活動は活発で、昭和30年(1955)に爆発した南岳山頂火口は、現在まで長期にわたり毎年のように噴火を繰り返しています。
2.代表的な噴火
① 大正大噴火
大正3年(1914)1月12日午前10時5分、噴火は桜島の西側山腹に出来た割れ目で始まり、10分後には東側山腹に出来た割れ目でも噴火が起きました。これら東西の火口からの噴煙は高度8,000mに達し、東海岸では数日で2mもの軽石が降りました。また大量のマグマを噴出し、溢れ出た溶岩流が麓の集落を襲い、死者58名、負傷者112名、噴火により埋没・全焼した家屋も約2140戸となり、集落ごと埋もれてしまった村もありました。この大正大噴火により、溢れ出した溶岩流により大隅半島との間の海峡が堰き止められ、現在のように陸続きになりました。
この時は噴火の数日前から地震が頻発し、島内の井戸が枯れるなどの異常があり、当時の村役場が対岸の鹿児島市にある測候所に問い合わせましたが、「避難せよ」という意見はなく、このような結果を招いてしまいました。10年後、住民達は桜島爆発記念碑を建て、裏に「住民は理論を信頼せず、異変を見つけたら、事前に避難の用意をすることが肝要である」と刻みました。避難誘導が遅れたのは、噴火を予知できなかった測候所に頼ったためと考えたからです。これは「科学不信の碑」とも呼ばれています。
② 昭和噴火
大正噴火が終息した後の約20年間は穏やかな状態でしたが、昭和10年(1935)9月、南岳東側山腹に新たな火口が形成され、約1ヶ月間断続的に噴火を繰り返すようになりました。
昭和21年(1946)1月から爆発が頻発するようになり、同年3月9日に火口から溶岩の流下が始まりました。この時は大正噴火とは異なり、噴火前後の有感地震が殆どありませんでした。
昭和29年(1954)12月末頃から火山性地震が増加し、昭和30年(1947)10月に南岳山頂火口で大量の噴石を噴出する爆発と、強烈な空震を伴う噴火があり、死者1名、負傷者11名を出しました。昭和47年(1972)の噴火では、噴出した高温の噴石により山火事が発生。これがきっかけとなり、被害者を守る「火山活動対策特別措置法」が制定されました。
平成18年(2006)6月には、南岳の東山腹8合目の昭和火口が58年ぶりに噴火活動を再開するなど、活発な活動状況が続いています。
3.現在の活動状況
2009年10月以降、年間爆発回数が1000回を超えるほど活動が活発な桜島ですが、2007年に運用が開始された噴火警戒レベルが、初めてのレベル4(避難準備)に引き上げられました。現在は火口3km圏内に住む51世帯77人が対象ですが、これまでの噴火の規模を上回る噴火が起きた場合、噴火警戒レベル5(避難)に引き上げ、鹿児島市が桜島全域の住民を避難させる事態も想定しています。
2015年8月15日午前7時頃から火山性地震が急増し、15日は1024回、16日は71回、17日は17回、20日午前9時までに8回まで減ってきていますが、マグマが浅い所まで上昇したまま止まっているとみられ、山体が膨張した状態が続いています。陸域観測衛星「だいち2号」の観測によると、今年1月に比べて最大16cm程度の地殻変動があったことも確認されました。また15日からは桜島の二俣港で、火山性ガスが海面に湧出する「たぎり」と呼ばれる現象が出現しました。これは鹿児島湾内の若尊カルデラで通常見られる現象ですが、二俣港では初めて出来事です。
幸いなことに規模の大きな噴火の可能性は低下してきているようですが、自然の活動は私達人間の思うようにはいきません。桜島の噴火特性から「落ち着いた状態は噴火が起こらないのではなく、むしろ噴火に近付いたと考えた方がいい」と警鐘を鳴らす専門家もいます。油断をすることなく備えていきたいと思います。
最後に、桜島関連情報をまとめたサイトを紹介します。
「桜島の噴火活動に関する情報」サイトへ移動!クリック!
火山灰に対する防災情報もありますので、ご参考になれば幸いです。
今回は、8月22日現在、噴火警戒レベル4(避難準備)が出されている桜島について取り上げてみたいと思います。
1.桜島の成り立ち
桜島は、鹿児島湾北奥部の姶良カルデラ南縁部に生じた東西約10km、南北約8kmの長円形の島で、その頂部は最高峰の北岳と中岳、南岳の3峰と権現山、鍋山、引ノ平などの側火山からなっています。
桜島が活動を開始したのは、姶良カルデラが大噴火した後の約26,000年前からで、初めは海底火山だったものが大規模な噴火を繰り返して、隆起して島になりました。現在までに大規模な噴火を17回繰り返しており、その中での最大の噴火は、今から約13,000年前の大噴火で、この時には現在の鹿児島市内で1m以上、鹿児島県内の殆どの箇所で10cm以上の火山灰が積もりました。
桜島の活動は大きく二つの時期に分かれており、誕生から5000年前までが北岳の活動、約4500年前からは南岳を中心とした活動期に入り、断続的な噴火と静穏な状態を繰り返しています。有史以後の山頂噴火は南岳で起こっており、その都度、溶岩流や火砕流による大災害となっています。
記録に残る主な活動としては、最古の噴火は和銅元年(708)、15世紀後半の文明大噴火、安永8年(1779)の安永大噴火があり、噴石や降灰により多数の死者を出しています。この安永大噴火は18世紀の日本最大の噴火で、海底噴火による津波が発生し、鹿児島県沿岸部でも多くの被害が生じました。更に大正3年(1914)の大正大噴火、また昭和に入ってからも噴火活動は活発で、昭和30年(1955)に爆発した南岳山頂火口は、現在まで長期にわたり毎年のように噴火を繰り返しています。
2.代表的な噴火
① 大正大噴火
大正3年(1914)1月12日午前10時5分、噴火は桜島の西側山腹に出来た割れ目で始まり、10分後には東側山腹に出来た割れ目でも噴火が起きました。これら東西の火口からの噴煙は高度8,000mに達し、東海岸では数日で2mもの軽石が降りました。また大量のマグマを噴出し、溢れ出た溶岩流が麓の集落を襲い、死者58名、負傷者112名、噴火により埋没・全焼した家屋も約2140戸となり、集落ごと埋もれてしまった村もありました。この大正大噴火により、溢れ出した溶岩流により大隅半島との間の海峡が堰き止められ、現在のように陸続きになりました。
この時は噴火の数日前から地震が頻発し、島内の井戸が枯れるなどの異常があり、当時の村役場が対岸の鹿児島市にある測候所に問い合わせましたが、「避難せよ」という意見はなく、このような結果を招いてしまいました。10年後、住民達は桜島爆発記念碑を建て、裏に「住民は理論を信頼せず、異変を見つけたら、事前に避難の用意をすることが肝要である」と刻みました。避難誘導が遅れたのは、噴火を予知できなかった測候所に頼ったためと考えたからです。これは「科学不信の碑」とも呼ばれています。
② 昭和噴火
大正噴火が終息した後の約20年間は穏やかな状態でしたが、昭和10年(1935)9月、南岳東側山腹に新たな火口が形成され、約1ヶ月間断続的に噴火を繰り返すようになりました。
昭和21年(1946)1月から爆発が頻発するようになり、同年3月9日に火口から溶岩の流下が始まりました。この時は大正噴火とは異なり、噴火前後の有感地震が殆どありませんでした。
昭和29年(1954)12月末頃から火山性地震が増加し、昭和30年(1947)10月に南岳山頂火口で大量の噴石を噴出する爆発と、強烈な空震を伴う噴火があり、死者1名、負傷者11名を出しました。昭和47年(1972)の噴火では、噴出した高温の噴石により山火事が発生。これがきっかけとなり、被害者を守る「火山活動対策特別措置法」が制定されました。
平成18年(2006)6月には、南岳の東山腹8合目の昭和火口が58年ぶりに噴火活動を再開するなど、活発な活動状況が続いています。
3.現在の活動状況
2009年10月以降、年間爆発回数が1000回を超えるほど活動が活発な桜島ですが、2007年に運用が開始された噴火警戒レベルが、初めてのレベル4(避難準備)に引き上げられました。現在は火口3km圏内に住む51世帯77人が対象ですが、これまでの噴火の規模を上回る噴火が起きた場合、噴火警戒レベル5(避難)に引き上げ、鹿児島市が桜島全域の住民を避難させる事態も想定しています。
2015年8月15日午前7時頃から火山性地震が急増し、15日は1024回、16日は71回、17日は17回、20日午前9時までに8回まで減ってきていますが、マグマが浅い所まで上昇したまま止まっているとみられ、山体が膨張した状態が続いています。陸域観測衛星「だいち2号」の観測によると、今年1月に比べて最大16cm程度の地殻変動があったことも確認されました。また15日からは桜島の二俣港で、火山性ガスが海面に湧出する「たぎり」と呼ばれる現象が出現しました。これは鹿児島湾内の若尊カルデラで通常見られる現象ですが、二俣港では初めて出来事です。
幸いなことに規模の大きな噴火の可能性は低下してきているようですが、自然の活動は私達人間の思うようにはいきません。桜島の噴火特性から「落ち着いた状態は噴火が起こらないのではなく、むしろ噴火に近付いたと考えた方がいい」と警鐘を鳴らす専門家もいます。油断をすることなく備えていきたいと思います。
最後に、桜島関連情報をまとめたサイトを紹介します。
「桜島の噴火活動に関する情報」サイトへ移動!クリック!
火山灰に対する防災情報もありますので、ご参考になれば幸いです。