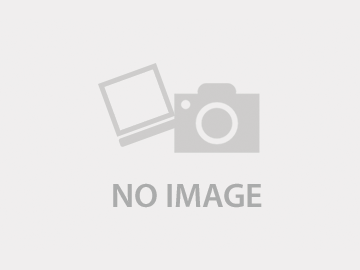新暦7月27日(旧暦6月12日 辰)
皆様 日々の祈り合わせに共にお心を合わせていただき
ありがとうございます。
本日は自然災害チームより 皆さまへ知っていただきたい記事を
掲載しております。 ぜひお読みになって下さい。
※ 以下 自然災害チームより
メルマガ読者のみなさま、こんにちは。
地球上で起きている様々な出来事に気づき学ぶことが
大切であると、比嘉良丸氏は常々お話の中で伝えています。
そこで、私たちはいくつかのチームに分かれて学び合って得た
情報等を、メルマガ読者の皆様とも共有したいと思っております。
自然災害チームからは、地球上の様々な自然の環境や災害に関連
することをお伝えします。
改めて日本列島を成り立ちや自然界の仕組み、私たちの身の回りや
日本・世界で起きていることに目を向け、私たちが何をしなければ
ならないのかを一緒に見つめ直し考えていけたらと思います。
自然災害チームのメンバー各々が書きますので、様々な視点からの
情報発信になると思います。
ひとつでも日常生活の中で活かすことのできる情報や話題として、
また、ご家族で防災を考えるきっかけになりましたら幸いです。
今回は上記に書きましたとおり、自然災害を知る上で必要な基礎的
な知識として「地震発生の仕組み」をお伝えします。
日本は地震大国と言われていますが、日本気象協会のデータを見る
と全国で毎日何度も地震が発生していることがわかります。
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/
そして地震に関連する様々なことを調べれば調べるほど、
母なる大地・地球のしくみは不思議に感じられます。
<地球の構造>
まずは、地球の構造から始めたいと思います。
現在の地球科学では「プレートテクトニクス」という理論により、
プレートの動きが説明されています。
私たちが立っている大地、地球の内部構造は
「半熟ゆで卵」に例えられ、大きく分けて中心から
「①核」「②マントル」「③地殻」からできています。
* 地球:半径約6400km
①核(内核・外核): 厚さ約3500km、温度約6000度。
内核は固体、外核は液体。(卵の黄身)
②マントル: 厚さ約2800km、固体ではあるが上層が
一部高温で柔らかい。最上部がプレート。(卵の白身)
③地殻: 海や陸地が乗っている。(卵の殻)
<プレート>
「マントル」の最上部の約100キロメートルの厚さの岩石が
「プレート」 と呼ばれています。
海底には、地上よりも大きな山や谷があり、その多くはプレートの
動きにより作られています。
プレートは、海嶺や海膨(海嶺より低い)と呼ばれる海底の高まり
から生まれ、マントルの深い部分が核で熱せられると 上向きに
流れ(ホットプルーム)、地表で冷やされたマントルは下浮きに流れ
(コールドプルーム)、マントルの中で 円を描くような流れによって、
海嶺の両側に水平方向に移動し、海溝に沈み込むと考えられています。
地球の表面は10数枚の厚いプレートで覆われ、
日本はそのうちの4枚の上に乗っています。
海を乗せている海洋プレート
(太平洋プレート、フィリピン海プレート)と、
大陸を乗せている大陸プレート
(ユーラシアプレート、北米プレート)があり、
それぞれ1年間に数cmのスピードでバラバラの方向に水平に
動いています。
そのため境界ではプレート同士が離れたり、ぶつかったり、
ずれたりして、海底や地上に大きな山や谷を作っています。
◆両側に離れ裂けた場所(海嶺・地溝帯)
◆海洋プレートが大陸プレートに沈み込む場所(海溝・トラフ)
・海溝:水深6000~10000mの急斜面の溝
・トラフ:水深6000mより浅い緩やかな谷)
◆プレート同士がすれ違う場所(トランスフォーム断層)
<日本列島>では、日本列島やその周辺はどうなっているのかを
見ていきたいと思います。
日本列島はプレート同士がぶつかり合体して形成されており、
4つのプレートがひしめいています。(*プレートを参照)
プレート境界には海溝やトラフ、構造線などが多くあり、
大地の仕組みは複雑で、世界の中でも日本は地震が多い要因となっています。
2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震により、
地震と津波に襲われ、日本列島の広い範囲で被害が出ました。
また、福島第一原子力発電所事故による二次被害は、今も心と体に
大きな影響を与えていることも忘れることは出来ません。
そこで今回は、日本列島や周辺地域の中から範囲を絞り、
北海道から伊豆半島までの太平洋側を中心に調べることに
しました。
<北海道から伊豆半島東側:太平洋側>
(海溝・トラフ)
日本列島の太平洋側沖(北海道から伊豆半島東側)には、
千島列島の南側に沿って北海道南東部まで続く千島海溝、
襟裳岬で曲がり房総半島まで続く日本海溝、さらに房総半島沖
から南東方向に伊豆・小笠原海溝へと帯のように海溝が繋がっています。
房総半島沖はフイリピン海プレートが西南日本に沈み込み、
太平洋プレートにも沈み込む3つの海溝
(日本海溝、相模トラフ、伊豆・小笠原海溝)が集まり、
フィリピン海プレートと太平洋プレートの境界で双方のプレートが
北米プレートに潜り込み、プレート端面が3つ重なる
「三重会合点」と呼ばれる場所です。
◆千島海溝: 北海道東部沖合にある太平洋プレートが陸側の
プレートに沈み込む場所。
◆日本海溝: 三陸沖の日本海溝からは、太平洋プレートが
東北日本に潜り込んでいて、関東南東沖合にある日本海溝
からは、太平洋プレートが伊豆・小笠原海溝の下に潜り込んでいます。
◆伊豆・小笠原海溝: フィリピン海プレートに太平洋プレートが沈み込む場所。
◆相模トラフ: フィリピン海プレートが本州の大陸プレートに 沈み込む場所。
(海山)
千島・カムチャッカ海溝と日本海溝がぶつかり折れ曲がった辺りにある
襟裳海山(高さ4200m)は、太平洋プレートに乗って南側
から移動してきていることが判明しており、今後は山が崩れて
陸のプレートに潜り沈むと考えられています。
日本海溝と伊豆・小笠原海溝がぶつかる茨城県沖にある
第1鹿島海山(高さ3300m)は、西半分が崩れて海溝に落ち込み、
付近の海山も海溝に向かっています。
また、伊豆半島南から伊豆・小笠原海溝に沿って弓なりに連なる
大きな海底山脈「伊豆・小笠原弧(幅300~400km、長さ1100km)」
には、八丈島、神津島、父島、母島、硫黄島などがあり、高いもの
は海面から出ています。ここは沢山の海底火山があり、
2013年には西ノ島付近の海底噴火で新しい島ができました。
(地震)
冒頭にも書きましたが、日本列島と周辺では、人が感じない地震
も含めて、毎日どこかで地震が起きています。
海溝などのプレートの境目に地震が多く発生していることが過去
の記録からもわかります。
プレートの動きにより、地震がどのように起きるのかを見ていきましょう。
◆内陸型地震: 沈み込む海洋プレートにより、大陸プレート中に
蓄積されたたわみが限界となり、 プレートが跳ね上がる前に
大陸プレートの内陸部が壊れて起きる。
逆断層や横ずれ断層を起こし、被害が大きくなる場合がある。
・兵庫県南部地震(1995年、M7.2)、新潟県中越地震(2007年、M6.8)
◆アウターライズ地震: 海溝型地震発生後にプレートの沈み込み
への抵抗力が小さくなり、アウターライズ(海溝の外側隆起帯)
と海溝の間の曲がりによるプレートの引っ張る力で正断層が発達し起きる。
震源は陸から離れていて地震動は小さくても、断層が海底に
達する場合は巨大津波が発生する可能性がある。
・明治三陸地震(1896年、M8.5)、昭和三陸地震(1933年、M8.1)
◆海溝型地震: 沈み込む海洋プレートが大陸プレートに沈み込む
時、大陸プレートに蓄積したたわみが限界となり元に戻ろうとして
跳ねあがり起きる。
逆断層が生じて巨大地震となる場合が 多い。
・東北地方太平洋沖地震(2011年、M9.0)、
大正関東地震(1923年、 M7.9)、
昭和南海地震(1946年M8.0)、昭和東南海地震(1944年、M7.9)、
安政東海地震(東海東南海連動・1854年、M8.6)
参考(海外):チリ地震(1960年、M9.5)、スマトラ地震(2004年、M9.1)
◆深発地震: 数十から数百キロの深さに沈み込むプレートの表面
付近で発生する。プレートの自重による張引力で正断層ができることが原因。
・釧路沖地震(1993年、M7.5)、北海道東方沖地震(1994年M8.2)
東北地方太平洋沖地震の前震とみられる3月9日のM7.3の地震は、
2002年から2009年にかけて多くの地震が発生した場所を震源と
して発生し、この場所ではM6クラスの地震がしばしば発生して
いました。
また、本震発生後に広範囲で影響したと考えられるM5.0以上の
誘発地震や余震は、本震発生後の1年間で650回を超え今でも
発生しています。
地震は、同じ震源域で過去に何度も繰り返し発生しており、周期の
長さからの想定予測にも注視していかなければなりません。
なお、マグニチュード(M)は1大きくなるとエネルギーは、
なんと、32倍(2大きくなると約1000倍!)になり、地震波や津波で
言うと10倍、震度については1上がると揺れの強さは2倍となります。
(津波)
海底地下の浅い部分で地震が起きると、海底面が盛り上がったり
沈んだりする時に、海面も同時に動いて起きた波が四方八方に
広がり津波になります。津波は水深が深いと速度は速く、浅いと
遅くなり、海岸付近は遅い波に速い波が追いついて合わさり高く
なることがあります。
V字やU字型など入り組んだ湾は、色んな方向から津波が集中
して押し寄せるため一気に高くなる傾向があり、波は浅い方へ
曲がる性質のため、水深が浅い岬の先に高い津波が集中します。
東北地方太平洋沖地震では、岩手県大船渡市綾里湾で40.1m
の津波が達したものが最大と見られており、この記録は明治三陸
地震の最大記録38.2m((同じ綾里地区)を上回り、明和の大津波
(発生当時は琉球)を除けば、日本で記録された最大の遡上高
でした。
また、東北地方だけでなく北海道の太平洋岸で1-3.5m程度、
千葉~九州の太平洋沿岸で1-3m程度、日本海側でも1m未満と
広範囲で観測されました。東北大学教授の今村文彦氏は、NHKが
仙台市若林区で撮影した津波の映像を分析し、津波の速さは
沿岸から1km内陸の地点では秒速約6m・ 時速20km以上であった
と明らかにしていますが、あっという間に海から陸に到達したと
わかります。
<最後に>
「地震発生の仕組み」としてお伝えしましたが、自然界の仕組みは
複雑なため、纏まらずに読みにくい、わかりにくい点があったこと
と思います。
高校生時代の地学の授業内容さえ覚えておらず、この場をお借り
して学び直しをさせていただいたと思っております。
調べていた時に少し気になったことがありますので、
最後にお伝えしたいと思います。
北海道の太平洋側では、東北地方太平洋沖地震の時に津波が
確認されましたが、人工的な港湾や防潮護岸などにより海岸が
変わっている箇所では局所的に9メートルを観測しています。
人間が便利に暮らすための都合で、自然環境を変えてしまったこと
が自然災害にも影響があるということかと思います。
私たちは経験を忘れることなく、そこから学んだ教訓を活かして
いかなければとならないと感じました。
図面を入れることができないため、長文での説明となりました
ことをお許しください。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
皆様 日々の祈り合わせに共にお心を合わせていただき
ありがとうございます。
本日は自然災害チームより 皆さまへ知っていただきたい記事を
掲載しております。 ぜひお読みになって下さい。
※ 以下 自然災害チームより
メルマガ読者のみなさま、こんにちは。
地球上で起きている様々な出来事に気づき学ぶことが
大切であると、比嘉良丸氏は常々お話の中で伝えています。
そこで、私たちはいくつかのチームに分かれて学び合って得た
情報等を、メルマガ読者の皆様とも共有したいと思っております。
自然災害チームからは、地球上の様々な自然の環境や災害に関連
することをお伝えします。
改めて日本列島を成り立ちや自然界の仕組み、私たちの身の回りや
日本・世界で起きていることに目を向け、私たちが何をしなければ
ならないのかを一緒に見つめ直し考えていけたらと思います。
自然災害チームのメンバー各々が書きますので、様々な視点からの
情報発信になると思います。
ひとつでも日常生活の中で活かすことのできる情報や話題として、
また、ご家族で防災を考えるきっかけになりましたら幸いです。
今回は上記に書きましたとおり、自然災害を知る上で必要な基礎的
な知識として「地震発生の仕組み」をお伝えします。
日本は地震大国と言われていますが、日本気象協会のデータを見る
と全国で毎日何度も地震が発生していることがわかります。
http://www.tenki.jp/bousai/earthquake/
そして地震に関連する様々なことを調べれば調べるほど、
母なる大地・地球のしくみは不思議に感じられます。
<地球の構造>
まずは、地球の構造から始めたいと思います。
現在の地球科学では「プレートテクトニクス」という理論により、
プレートの動きが説明されています。
私たちが立っている大地、地球の内部構造は
「半熟ゆで卵」に例えられ、大きく分けて中心から
「①核」「②マントル」「③地殻」からできています。
* 地球:半径約6400km
①核(内核・外核): 厚さ約3500km、温度約6000度。
内核は固体、外核は液体。(卵の黄身)
②マントル: 厚さ約2800km、固体ではあるが上層が
一部高温で柔らかい。最上部がプレート。(卵の白身)
③地殻: 海や陸地が乗っている。(卵の殻)
<プレート>
「マントル」の最上部の約100キロメートルの厚さの岩石が
「プレート」 と呼ばれています。
海底には、地上よりも大きな山や谷があり、その多くはプレートの
動きにより作られています。
プレートは、海嶺や海膨(海嶺より低い)と呼ばれる海底の高まり
から生まれ、マントルの深い部分が核で熱せられると 上向きに
流れ(ホットプルーム)、地表で冷やされたマントルは下浮きに流れ
(コールドプルーム)、マントルの中で 円を描くような流れによって、
海嶺の両側に水平方向に移動し、海溝に沈み込むと考えられています。
地球の表面は10数枚の厚いプレートで覆われ、
日本はそのうちの4枚の上に乗っています。
海を乗せている海洋プレート
(太平洋プレート、フィリピン海プレート)と、
大陸を乗せている大陸プレート
(ユーラシアプレート、北米プレート)があり、
それぞれ1年間に数cmのスピードでバラバラの方向に水平に
動いています。
そのため境界ではプレート同士が離れたり、ぶつかったり、
ずれたりして、海底や地上に大きな山や谷を作っています。
◆両側に離れ裂けた場所(海嶺・地溝帯)
◆海洋プレートが大陸プレートに沈み込む場所(海溝・トラフ)
・海溝:水深6000~10000mの急斜面の溝
・トラフ:水深6000mより浅い緩やかな谷)
◆プレート同士がすれ違う場所(トランスフォーム断層)
<日本列島>では、日本列島やその周辺はどうなっているのかを
見ていきたいと思います。
日本列島はプレート同士がぶつかり合体して形成されており、
4つのプレートがひしめいています。(*プレートを参照)
プレート境界には海溝やトラフ、構造線などが多くあり、
大地の仕組みは複雑で、世界の中でも日本は地震が多い要因となっています。
2011年3月に発生した東北地方太平洋沖地震により、
地震と津波に襲われ、日本列島の広い範囲で被害が出ました。
また、福島第一原子力発電所事故による二次被害は、今も心と体に
大きな影響を与えていることも忘れることは出来ません。
そこで今回は、日本列島や周辺地域の中から範囲を絞り、
北海道から伊豆半島までの太平洋側を中心に調べることに
しました。
<北海道から伊豆半島東側:太平洋側>
(海溝・トラフ)
日本列島の太平洋側沖(北海道から伊豆半島東側)には、
千島列島の南側に沿って北海道南東部まで続く千島海溝、
襟裳岬で曲がり房総半島まで続く日本海溝、さらに房総半島沖
から南東方向に伊豆・小笠原海溝へと帯のように海溝が繋がっています。
房総半島沖はフイリピン海プレートが西南日本に沈み込み、
太平洋プレートにも沈み込む3つの海溝
(日本海溝、相模トラフ、伊豆・小笠原海溝)が集まり、
フィリピン海プレートと太平洋プレートの境界で双方のプレートが
北米プレートに潜り込み、プレート端面が3つ重なる
「三重会合点」と呼ばれる場所です。
◆千島海溝: 北海道東部沖合にある太平洋プレートが陸側の
プレートに沈み込む場所。
◆日本海溝: 三陸沖の日本海溝からは、太平洋プレートが
東北日本に潜り込んでいて、関東南東沖合にある日本海溝
からは、太平洋プレートが伊豆・小笠原海溝の下に潜り込んでいます。
◆伊豆・小笠原海溝: フィリピン海プレートに太平洋プレートが沈み込む場所。
◆相模トラフ: フィリピン海プレートが本州の大陸プレートに 沈み込む場所。
(海山)
千島・カムチャッカ海溝と日本海溝がぶつかり折れ曲がった辺りにある
襟裳海山(高さ4200m)は、太平洋プレートに乗って南側
から移動してきていることが判明しており、今後は山が崩れて
陸のプレートに潜り沈むと考えられています。
日本海溝と伊豆・小笠原海溝がぶつかる茨城県沖にある
第1鹿島海山(高さ3300m)は、西半分が崩れて海溝に落ち込み、
付近の海山も海溝に向かっています。
また、伊豆半島南から伊豆・小笠原海溝に沿って弓なりに連なる
大きな海底山脈「伊豆・小笠原弧(幅300~400km、長さ1100km)」
には、八丈島、神津島、父島、母島、硫黄島などがあり、高いもの
は海面から出ています。ここは沢山の海底火山があり、
2013年には西ノ島付近の海底噴火で新しい島ができました。
(地震)
冒頭にも書きましたが、日本列島と周辺では、人が感じない地震
も含めて、毎日どこかで地震が起きています。
海溝などのプレートの境目に地震が多く発生していることが過去
の記録からもわかります。
プレートの動きにより、地震がどのように起きるのかを見ていきましょう。
◆内陸型地震: 沈み込む海洋プレートにより、大陸プレート中に
蓄積されたたわみが限界となり、 プレートが跳ね上がる前に
大陸プレートの内陸部が壊れて起きる。
逆断層や横ずれ断層を起こし、被害が大きくなる場合がある。
・兵庫県南部地震(1995年、M7.2)、新潟県中越地震(2007年、M6.8)
◆アウターライズ地震: 海溝型地震発生後にプレートの沈み込み
への抵抗力が小さくなり、アウターライズ(海溝の外側隆起帯)
と海溝の間の曲がりによるプレートの引っ張る力で正断層が発達し起きる。
震源は陸から離れていて地震動は小さくても、断層が海底に
達する場合は巨大津波が発生する可能性がある。
・明治三陸地震(1896年、M8.5)、昭和三陸地震(1933年、M8.1)
◆海溝型地震: 沈み込む海洋プレートが大陸プレートに沈み込む
時、大陸プレートに蓄積したたわみが限界となり元に戻ろうとして
跳ねあがり起きる。
逆断層が生じて巨大地震となる場合が 多い。
・東北地方太平洋沖地震(2011年、M9.0)、
大正関東地震(1923年、 M7.9)、
昭和南海地震(1946年M8.0)、昭和東南海地震(1944年、M7.9)、
安政東海地震(東海東南海連動・1854年、M8.6)
参考(海外):チリ地震(1960年、M9.5)、スマトラ地震(2004年、M9.1)
◆深発地震: 数十から数百キロの深さに沈み込むプレートの表面
付近で発生する。プレートの自重による張引力で正断層ができることが原因。
・釧路沖地震(1993年、M7.5)、北海道東方沖地震(1994年M8.2)
東北地方太平洋沖地震の前震とみられる3月9日のM7.3の地震は、
2002年から2009年にかけて多くの地震が発生した場所を震源と
して発生し、この場所ではM6クラスの地震がしばしば発生して
いました。
また、本震発生後に広範囲で影響したと考えられるM5.0以上の
誘発地震や余震は、本震発生後の1年間で650回を超え今でも
発生しています。
地震は、同じ震源域で過去に何度も繰り返し発生しており、周期の
長さからの想定予測にも注視していかなければなりません。
なお、マグニチュード(M)は1大きくなるとエネルギーは、
なんと、32倍(2大きくなると約1000倍!)になり、地震波や津波で
言うと10倍、震度については1上がると揺れの強さは2倍となります。
(津波)
海底地下の浅い部分で地震が起きると、海底面が盛り上がったり
沈んだりする時に、海面も同時に動いて起きた波が四方八方に
広がり津波になります。津波は水深が深いと速度は速く、浅いと
遅くなり、海岸付近は遅い波に速い波が追いついて合わさり高く
なることがあります。
V字やU字型など入り組んだ湾は、色んな方向から津波が集中
して押し寄せるため一気に高くなる傾向があり、波は浅い方へ
曲がる性質のため、水深が浅い岬の先に高い津波が集中します。
東北地方太平洋沖地震では、岩手県大船渡市綾里湾で40.1m
の津波が達したものが最大と見られており、この記録は明治三陸
地震の最大記録38.2m((同じ綾里地区)を上回り、明和の大津波
(発生当時は琉球)を除けば、日本で記録された最大の遡上高
でした。
また、東北地方だけでなく北海道の太平洋岸で1-3.5m程度、
千葉~九州の太平洋沿岸で1-3m程度、日本海側でも1m未満と
広範囲で観測されました。東北大学教授の今村文彦氏は、NHKが
仙台市若林区で撮影した津波の映像を分析し、津波の速さは
沿岸から1km内陸の地点では秒速約6m・ 時速20km以上であった
と明らかにしていますが、あっという間に海から陸に到達したと
わかります。
<最後に>
「地震発生の仕組み」としてお伝えしましたが、自然界の仕組みは
複雑なため、纏まらずに読みにくい、わかりにくい点があったこと
と思います。
高校生時代の地学の授業内容さえ覚えておらず、この場をお借り
して学び直しをさせていただいたと思っております。
調べていた時に少し気になったことがありますので、
最後にお伝えしたいと思います。
北海道の太平洋側では、東北地方太平洋沖地震の時に津波が
確認されましたが、人工的な港湾や防潮護岸などにより海岸が
変わっている箇所では局所的に9メートルを観測しています。
人間が便利に暮らすための都合で、自然環境を変えてしまったこと
が自然災害にも影響があるということかと思います。
私たちは経験を忘れることなく、そこから学んだ教訓を活かして
いかなければとならないと感じました。
図面を入れることができないため、長文での説明となりました
ことをお許しください。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。